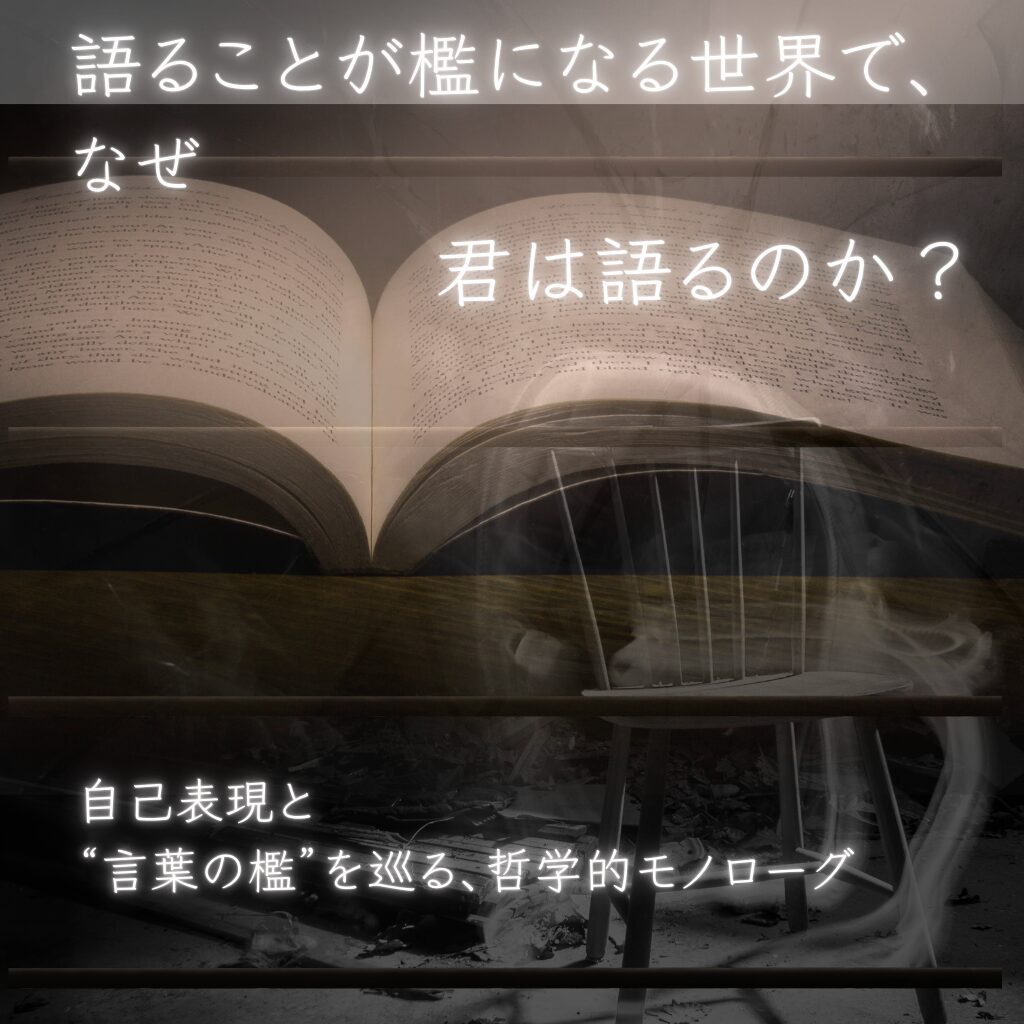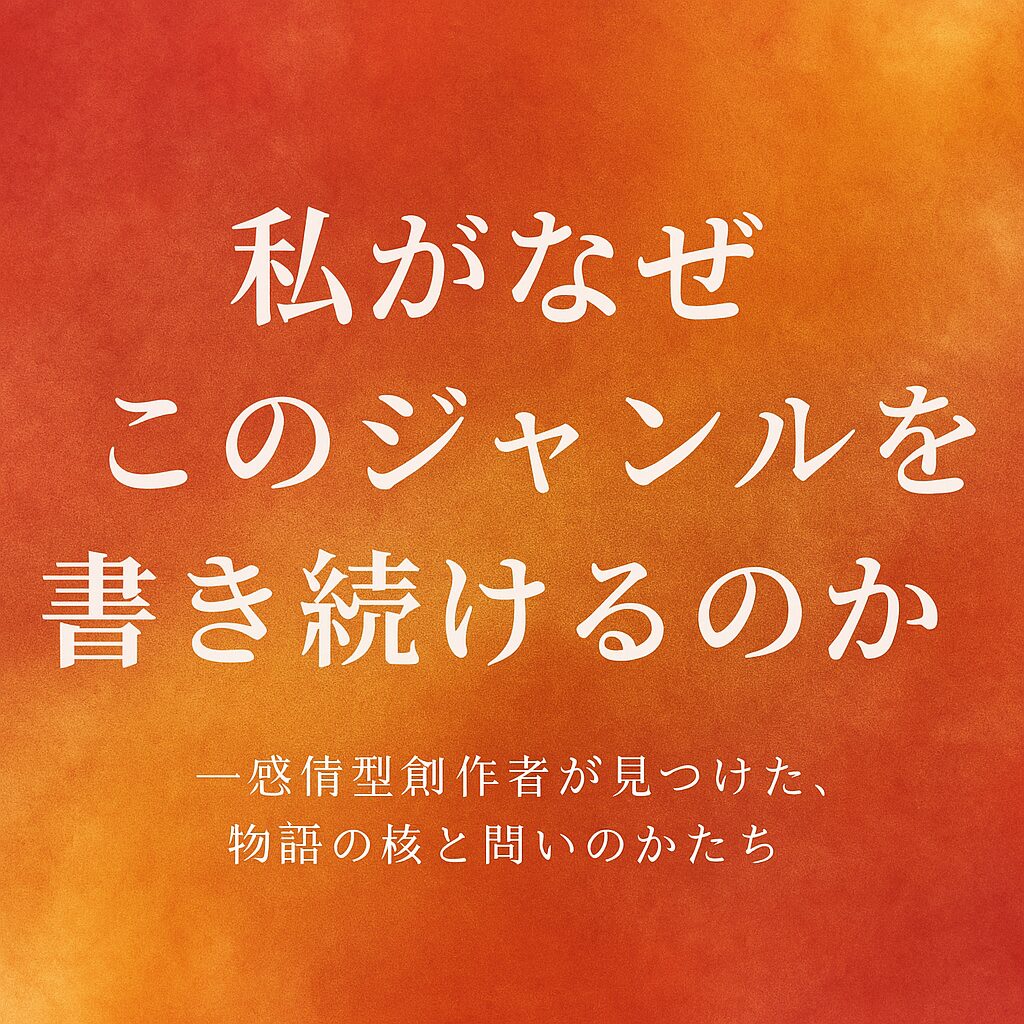総受け?ハーレム?──“感情の多面体”としての愛され主人公論

はじめに:なぜ今、愛され主人公を語るのか
「主人公総受け」「愛され系」「ハーレム構造」。 これらは一部で絶大な人気を誇りながらも、文脈によってはややネガティブな印象で語られることもあるジャンルだ。
特に主人公が複数キャラから想いを寄せられる“ハーレムもの”に関しては、「都合が良すぎる」「ご都合主義」といった否定的な意見も少なくない。
だが、感情を丁寧に描き込んだ「多面体としての愛され構造」は、単なる願望充足にとどまらず、“人間という存在の複雑さ”を浮き彫りにする可能性を秘めている。
この記事では、終夜が手がける一次創作の事例をもとに、「感情の多面体としての愛され主人公」を分析していく。
広義の“ハーレム”とは何か──誤解と偏見を超えて
本記事で扱う「ハーレム」は、いわゆるエロ主体・ギャグ主体のものではない。 あくまで感情的な結びつきの多面性として、「複数人から異なる愛が向けられる構造」を指している。
この構造では、主人公が「多数から想われる存在である」こと自体がテーマになっており、それぞれのキャラが異なる背景・価値観・感情からアプローチしてくる。まさに“感情の多面体”である。
そして、向けられる愛がすべて同じではないからこそ、
「同じ“好き”でも、誰一人として同じ気持ちではない」
という、人間の深みを描ける。
実例:ある一次創作作品に見る“愛のかたち”
終夜の創作する長編BLでは、主人公が複数のキャラクターから執着や愛を向けられる総受け構造を持っている。
が、それぞれのキャラが抱く感情の色はすべて異なる。
以下は、主人公に向けられる愛の種類を抽出・整理したものである(※物語のネタバレを避けるため、キャラ名は伏せて紹介する)。
キャラクター別:「感情の多面体」としての愛
- 幼なじみ(元ヤン)からの愛:
- 「懐かしさと愛おしさ」が混じった、“すとんと胸に落ちる愛”
- 無自覚なまま長年持ち続けていた想いが、再会を機に溢れ出す
- 寡黙な優等生からの愛:
- 「静かな情熱」がじわじわと外堀を埋めていく、“気づきの愛”
- 主人公が自覚した時には逃げ道がない、誠実ゆえの深さがある
- ストーカー気質の美形からの愛:
- 「幼さと独占欲」が混ざった、“愛でるような愛”
- 自分だけが理解者でありたいという欲が垣間見える
- 参謀系の冷静ポジからの愛:
- 「安全圏の裏に潜んでいた欲望」が不意打ちで現れる、“逃げ場を失わせる愛”
- 最も冷静な存在だと思っていた相手の、秘めた情動に揺さぶられる
- 年下の天才ヤンキーからの愛:
- 「初恋の熱」がまっすぐに向けられる、“常識を超えた憧憬の愛”
- 理屈ではなく感覚で主人公を“運命”と感じてしまう
これらの感情は、すべて“執着”や“欲”を起点にしている。 だが、誰一人として同じかたちではない。過去の経験、価値観、出会い方によって“愛の輪郭”は異なってくるのだ。
そしてその差異が、物語に豊かな厚みを与えている。
ハーレム作品が評価されにくい理由と、その乗り越え方
一般的に「ハーレム構造」が敬遠されがちなのは、以下のような懸念があるからだ:
- 主人公が不誠実に見えてしまう(=誰にでもいい顔する)
- キャラの“愛”が安っぽく感じられる(=なぜ惚れたかが描かれていない)
- 感情の描写が浅いと「数打ちゃ当たる」に見えてしまう
だが逆に言えば、これらを乗り越える鍵も明確だ。
- 主人公の「受け取り方」に誠実さを持たせる(=心の揺れや選択を描く)
- キャラの“背景”と“視点”を丁寧に描く(=愛の出自を示す)
- 感情の“原液”を濃く抽出する(=読者に「刺さる」体験を)
そのうえで、「誰を選ぶか」よりも「どのように受け止めたか」の感情の旅を主軸に据えることで、読者の共鳴が生まれる。
終夜の視点:「ちやほやされたいドン!」から始まった物語
興味深いのは、終夜本人の創作モチベーションが
「ちやほやされたいドン!」
という、きわめて素朴で正直な欲求からスタートしている点だ。
だが、実際に生み出されたキャラクターたちの感情や関係性は、どこまでも人間らしい。
人はなぜ他者を求めるのか? なぜ惹かれてしまうのか? なぜ“特別な存在”になってほしいと思うのか?
終夜作品における愛は、決して都合の良いハーレムファンタジーではない。 それぞれのキャラが、自分の人生・傷・後悔・願いを携えたまま、主人公という光に向かって手を伸ばしている。
そしてその“届かなさ”や“戸惑い”が、読者の胸を打つ。
おわりに:愛の多面体としての“総受け”を、もっと自由に描こう
愛とは、ひとつのかたちでは表現できない。
特に「総受け」「愛され主人公」「ハーレム構造」といったジャンルは、 ある意味で“人間の感情の多様性”そのものを物語に乗せるチャンスでもある。
終夜の描く世界が、それを証明している。
本記事が、“愛され主人公”という構造の可能性を見直すきっかけになれば嬉しい。
──そして、愛の多面体に囲まれながら白目をむく主人公を、 今日も私たちは愛してしまうのである。